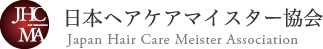美容業界において名誉と権威ある称号
JAPAN HAIR CARE MEISTER ASSOCIATION

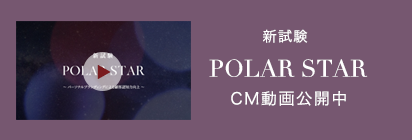
-
認定試験の
ご案内と申込みについて
-
プライマリー・ミドル合格者
ヘアケアマイスター認定者ページ開設
-
認定者
都道府県一覧ページ
-

- 公式LINE@ START!!
- 協会の最新情報など登録すると様々なメリットがあります。
-

- 第9回ヘアケアマイスター授与式レポート
- コロナの影響で4年越しの開催になった第九回授与式では、初の船上での授与式開催となりました。
-

- 合格者インタビュー
- 受験された方からの受験理由やサロンワークで変わったことなど受験者のインタビューを紹介します
-

- 2023年5月度 合格者発表
- ミドル・プライマリー・マイスター2次・ポーラスターコースの合格者番号の年度別発表をおこなっています
-
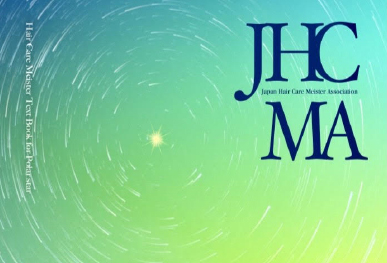
- 新試験 ポーラスターコースの解説動画
- 新試験「POLAR STAR|ポーラスター」のYouTubeCM+解説動画を公開中
-

- 認定制度について
- ヘアケアマイスター認定制度について詳しく掲載しています
- ヘアケアマイスターとは
- HAIR CARE MEISTER
- 美容業界において名誉と権威ある称号「ヘアケアマイスター」を解説
- 詳しくみる